戦傷病者として群馬県内で暮らす人は4人 この10年で大幅減
2025/5/16
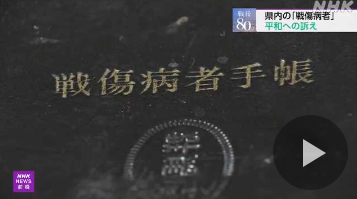
ことしで戦後80年となる中、太平洋戦争の際に戦場で負傷するなどした「戦傷病者」として県内で暮らす人は、この10年で大幅に減少し、ことし3月の時点でわずか4人となっていることが県への取材でわかりました。
国は、戦争で負傷したり病気になったりした軍人や軍関係者の「戦傷病者」に手帳を交付し、法律に基づいて療養費の給付などを行っています。
県によりますと、県内の戦傷病者は最も多かった1973年には2229人いましたが、年月を経るごとに減少が続いて10年前の2015年に410人となり、ことし3月の時点では4人となっているということです。
4人はいずれも元軍人で、平均年齢は99歳に達しているということです。
戦後80年となり、当時を知る人が少なくなる中、戦争の記憶や教訓を次の世代にどう伝えていくかが課題となっていて、ことしは前橋市や太田市で資料館がオープンするなど、各自治体が取り組みを強化しています。
県地域福祉課の米沢孝明課長は「戦争を経験している人は年々減少していて、戦争の記憶の風化を懸念している。戦争を2度と起こさないよう多くの人に戦争の悲惨さと平和の尊さを伝えていきたい」と話しています。
【戦傷病者が語る戦争と平和】
県内の「戦傷病者」の1人、前橋市内に住む石井義三さん(98)です。
1943年に16歳で志願して旧日本海軍に入隊し、翌年には当時日本が統治していた台湾の基地に派遣されてゼロ戦の機関銃を整備する任務に就きました。
そして、1944年10月、基地に襲来したアメリカ軍機に右足を撃たれて重傷を負い、足に障害が残ったということです。
石井さんは「戦友が乗るゼロ戦を基地から飛び立たせたあと、掩体壕に逃げ込もうとしたが間に合わず、地上をはっていたところ、足を撃ち抜かれた。おんぶしてもらい掩体壕に逃げ込めたが、大量に出血していて、『こういう風にして命を落としていくんだ』と思ったことを覚えている。戦友からの輸血でなんとか生き延びた」と負傷した当時の状況を語りました。
その後は、入院と転院を繰り返して秋田県で終戦を迎え、戦後は、父親がいた旧伊香保町に移り住んで町の公務員として定年まで勤め上げたということです。
石井さんの軍歴を記した資料には、本人の手書きで「若い搭乗員を送り出し、夕刻までに帰ってこない時ほど世の無常を感じたことはありません。平和が第一です」と記されています。
石井さんは「戦争が終わったとき、『戦争はするものじゃない』と強く思いました。命を戦争の用具として、兵器として利用したのは一番悪いことで、いまも許せないです」と話していました。
そのうえで「戦争のない現在の平和が、誰も努力をしないでできているものだと思うのは間違いだと思う。努力を重ねて、この平和が作られてきたと思うんです。“戦後”が80年も続いてきたのだから、そのことをよく考えてほしいです」と話していました。
—–
[cite] : 戦傷病者として群馬県内で暮らす人は4人 この10年で大幅減|NHK 群馬県のニュース